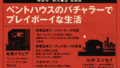石田衣良に灸を据える
昨日、テレビで全国警察剣道選手権大会を観た。女性警察官たちが、日本一をかけて真剣に竹刀を交える姿に、思わず見入ってしまった。
この大会を観ながら、僕は警察という組織の構造に思いを巡らせた。警察は、全国に展開する巨大な行政機関である。都道府県警察の職員は基本的に地方公務員だが、幹部以上の階級になると国家公務員となる。警察庁に所属する、いわゆる「キャリア組」は、国家公務員総合職試験を経て採用される。一方で、一般の大卒・高卒の職員も多く、組織内には明確な階層が存在する。
こうした階層の断絶を埋めるために、剣道大会のようなスポーツイベントが果たす役割は小さくないのではないか。大会で優れた成績を収めれば、職制とは異なる価値軸でその人物を評価できる。また、縦割りとされがちな警察組織において、都道府県を越えた横のつながりを育む場としても機能しているように思える。大会を通じて、県境を越えた友情や信頼が芽生えることもあるだろう。
僕の父は、かつて日本電信電話公社(旧・電々公社|現・NTT)の職員だった。最終的には都内の大規模電話局の局長を務めた。旧大蔵省でいえば主計課長に相当するような中間幹部職※である。父は東大出のキャリアではなく、東京の私立大学を卒業し、一般職として採用された。いわば、組織の中で一歩一歩、地道に階段を登っていった人間だった。(※中間幹部職は、中間管理職とは別の言葉)
春秋叙勲では名が挙がらなかったが、後年、高齢者叙勲で瑞宝双光章を受章した。亡くなった後には従六位の位階も授与された(叙位)。これは、長年の公務に対する国家からの敬意である。
役所というのは、民間企業と異なり、同じ「課長」でも地方の出先機関、県庁所在地の本部、そして東京の本省とでは、その重みがまったく異なる。霞が関の主計課長ともなれば、個室の執務室があり、受付の女性職員が応対する。これは民間企業でいえば、役員待遇に近い。
私見だが、役所の仕事は往々にして地味である。だからこそ、職員には働くための動機づけが必要であり、それがこのような複雑な職制を生んだのではないかと思う。
父は、局長候補100人の中から選ばれたと聞く。その競争を勝ち抜いて局長の座を射止めたのだ。一方で、キャリア組はこうした関門を難なく通過していく特急列車のような存在である。
父と暮らしながら、僕はその努力と誇りを間近で見てきた。父はよくいっていた。「たかが学歴だが、学歴は学歴だ」と。ダメンズの僕は自分の学歴を活かすことができなかったが、父の言葉は今も胸に残っている。
そんな中、作家の石田衣良氏が、若者向けのネット番組で語っていた。千葉県庁の職員が喫茶店で同僚の噂話をする際、必ずその人の学歴から話し始める。それが滑稽だと笑い、アシスタントの若手たちもそれに同調していた。
僕は思った。「石田さん、あんた作家だろッ!」人生の裏側まで想像し、描くのが仕事ではないのか。公の場で、人の努力の積み重ねを笑い飛ばすような発言をしてはダメだよ。
小倉 一純

「後記」
石田衣良氏は、僕と同年代の直木賞作家である。『池袋ウエストゲートパーク』で知られている。若者の心をつかむのが上手い、エンタメ系の商業作家だ。
学校群制度の只中にあった当時の都立高校トップ校を卒業し、成蹊大学に進んだ。受験にはまったく関心がなかったそうである。その後、CM制作会社にコピーライターとして就職した。仕事の相手がたとえ東大出でも、まったく負ける気がしなかったと述懐している。頭のいい人なのだろう。
ユーチューブで、恐らくは若者向けの番組を定期的に放送している。どちらかというと世事に疎い僕には、とても勉強になる番組だ。文学・音楽・漫画などを、エンタメ系という観点から上手に説明している。純文学系に関しては、「知っているけど、敢えて語らない」というスタンスである。
最近の文学は、ラノベから発生している。ラノベとはライトノベルズ。少女漫画がそもそもの源泉である。1970年代にその萌芽は見られる。『魔界転生』とか『ボーイズラブ』とか、そんな世界観の中での物語だ。
音楽はアニソン、つまりアニメソングが若者の心をつかんでいる(僕は詳細を知らない)。ラノベとアニソン、僕ら純文学世代(昭和世代)からは、かなり違和感のある分野ではある。でも、今の40代にしても、漫画やアニメ、それをモチーフにしたゲームで育っているのだから、そういう世界観が彼らの癒しになるのだろう。
そんな面を考えあわせると、それらを決して否定的には語れない。今度は逆に、僕が、若い人から叱られてしまう。