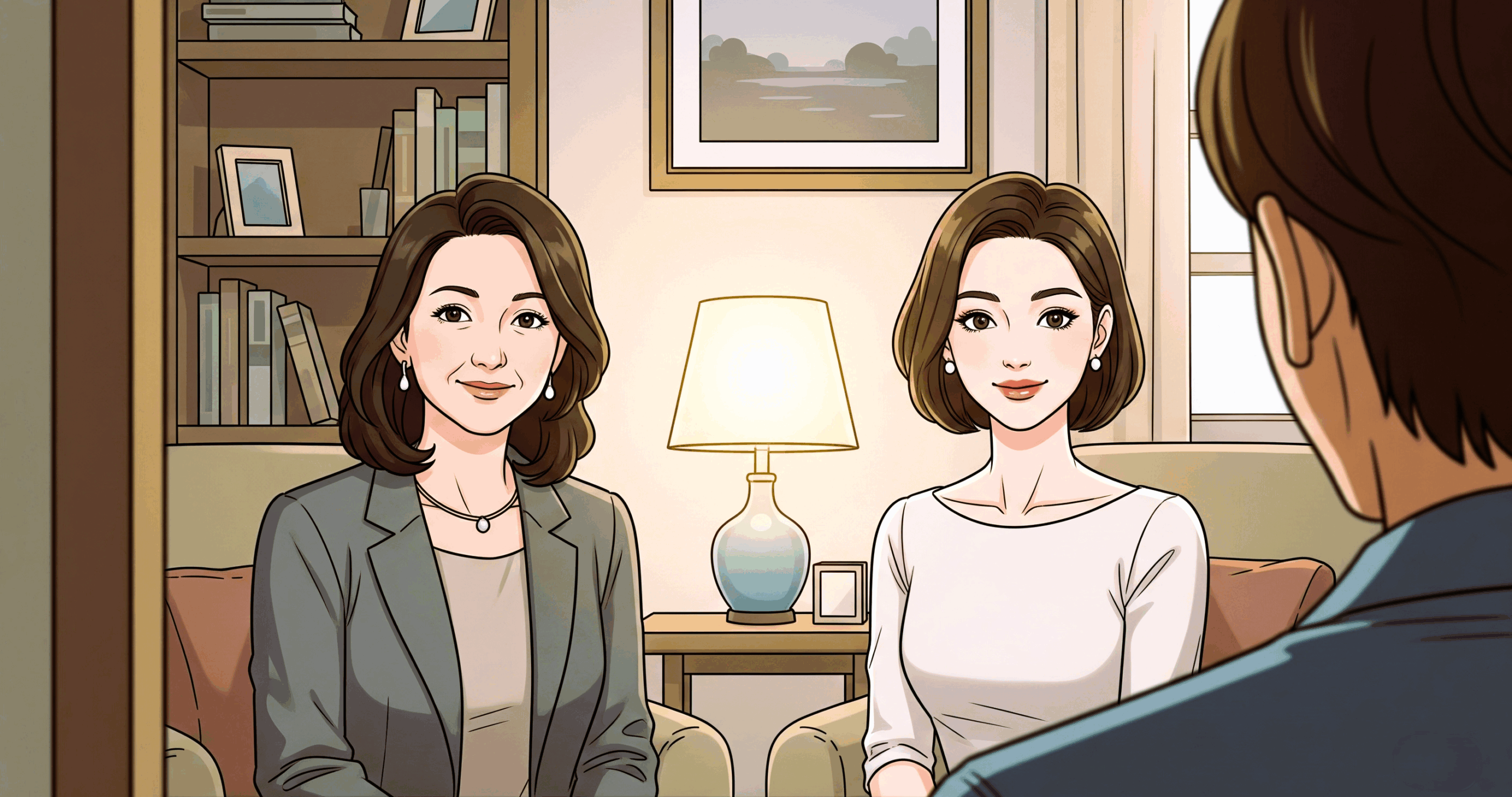一本、取られる!
——本当の承認欲求が満たされない時代——
彼女たちは、月に2度、我が家を訪れる。精神科医と精神保健福祉士。在宅医療という名の静かな往診。窓の外ではツクツク法師が鳴いている。
——往診、着く着くッ……
その日、リビングで向き合って腰を下ろした瞬間、僕は思った。
「(あれ、彼女、ずいぶんきれいになったな)」
髪型か、メイクなのか、何かが光っていた。
だから、僕はいった。
「あなたさ、この頃、きれいになったよね」
瞬間、空気が硬くなった。
若い彼女は笑ったが、医師がすぐに口を開いた。
「小倉さん、それ、今、セクハラとして一本取られますよ」
一本。
言葉が、まるで罰点のように数えられる時代。
66歳の僕は笑った。
「そうか、これも一本か」
でも、すぐに気が付いた。
これは、僕が患者だからこそ釘を刺されたのだろう。感情が揺れやすい者に対して、関係の境界を守らせるための、優しい牽制だったのかもしれない。
だから、僕は医師を責めない。むしろ、その一言に、彼女の誠実さを感じる。
ただ、それでも思う。
この社会では、誰が、どんな気持ちでいったかよりも、言葉そのものが、罰点の対象となる。関心は、加害に変わり、善意さえ、管理される。
人は互いに触れられなくなっていく。
昭和の時代なら、もっと自然に、「きれいだね」といえた。それは、関係の始まりであり、互いの存在を認め合う、ささやかな儀式だった。
でも今は、言葉が先に罰を背負ってしまう。承認は、ルールに沿ってしか与えられず、感情は、専門職の判断のもと、場面と適正が分類される。
こうして、言葉が裁かれ、感情が管理される社会では、人は本来の関係性を築くことが難しくなっていく。歌舞伎町のホストクラブに通う若い女性たちの気持ちもわかる気がする。問題は、人間関係の希薄さから起こっているのだろう。
—
文とCG:小倉 一純
【僕の考え】
この問題、ジャーナリズムの視点では「ルッキズム」という言葉があります。
外見による差別や評価の偏りが、就労・恋愛・教育などあらゆる場面に影響を及ぼしていることは、確かに深刻な問題です。
僕もその基本的な問題提起には賛成です。
しかし最近では、「かわいいね」「かっこいいね」といった日常的な感情表現すら、差別的だとされる風潮があり、それはさすがに行き過ぎではないかと感じる場面もあります。
人間の関係性には、外見に対する素朴な感情(赤ちゃんがかわいいとか)や、文化的な美意識(着物姿の女性がきれいだとか)も含まれていて、それらすべてを抑圧することが、かえって人と人とのつながりを希薄にしてしまうのではないか。
僕のように、ある種のコミュニケーション障害を抱えた人間のいうことではないかもしれませんが、だからこそ僕は、人と人との関係の希薄さには敏感にならざるを得ません。
この希薄さは、やがて国力の衰退へとつながると、僕は強く感じています。
極端な例ですが、かつてフランス※では、現在約6800万人の人口が、第二次世界大戦直後には約4000万人にまで落ち込みました。
戦争による死者や迫害、疫病などが影響し、政府は国力の再建に苦慮した時代でした。
この歴史は、人口の減少というものが、単なる統計ではなく、社会の活力や関係性の再構築を迫る問題であることを示しています。
時代は今、経済は左傾化し、文化は右傾化の兆候を見せています。つまり、経済面では格差是正や再分配が重視される一方、文化面では「男は男らしく、女は女らしく」といった性的役割の回帰が見られます。
要するに、時代は、振れ幅は分かりませんが、「きれいだね」「かわいいね」などの発言が許容される方向に動いているいうことです。もっとも、一度形成された概念的秩序が簡単になくなるとも思えませんけれども。
※フランスの歴史的事実は、僕が30代の時、あるクリスチャンの女性に教示されました。彼女=先生は、ご自分の母校である青山学院大学でフランスの歴史を研究し、一時は、博士号を取ろうとまで思っていたと伺っています。
(小倉 一純)