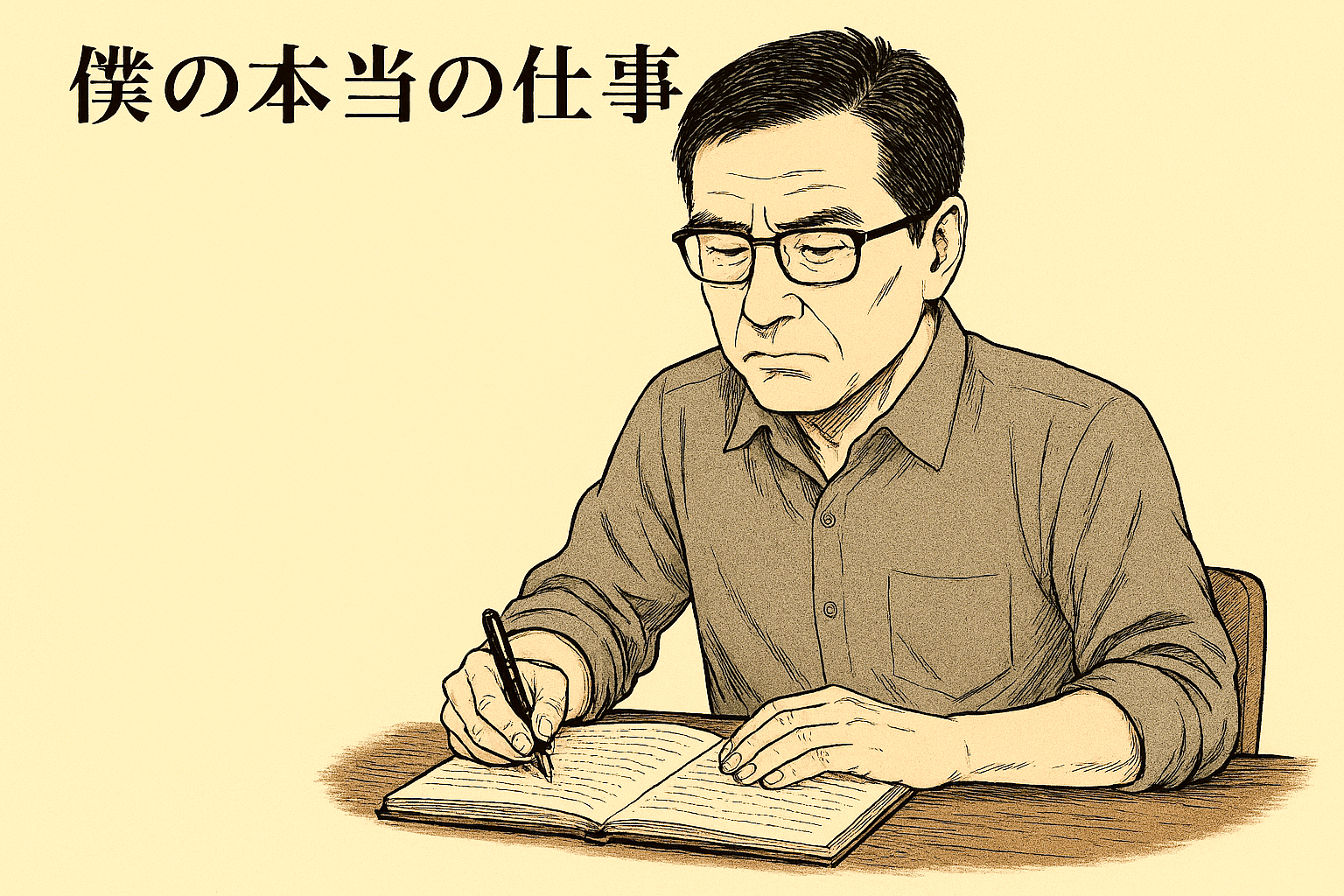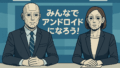僕の本当の仕事
僕には現在、特定の信仰はありません。とはいうものの、これまでにいろいろな宗教を経験しています。
仏教、神道、キリスト教と、ひととおりの道を歩いてきました。そんな環境の中で、僕は神仏に「どうか本当の事を教えてください」と毎日のように祈ったものでした。
「お金持ちになりたい」「幸せになりたい」「いい女とお近づきになりたい」——こういう気持ちはもちろんあります。人一倍かもしれません。しかし僕は、「どんなに苦労してもいいですから、人生とは、浮き世とは何なのか、本当のところを見せてください」と祈ってきました。
文学修行の道に入ってからは、「政治の話はいけない」「信教の話はタブーだ」と思ってきましたが、自分の中でこれだけ大きなウェイトを占めるものをオミットしてしまったのでは、何の作品も書けません。それに、『随筆春秋』はエッセイを書くところですから、自分の本当のところを語らなくてはいけません。
商業ベースに乗った小説家が、こんなことをいいます。
「エッセイは本当のことを書くのが原則だけど、私は20~30%はフィクションを織り交ぜるの」
「だってその方が面白くなるでしょ!」
随筆春秋ではご法度です。自分が臨場していない場面のセリフや登場人物の所作を、あたかも見てきたように綴ると、佐藤愛子先生の檄が飛びます。
「あなた、これ実際には見ていないんでしょ」
「どうしてもこういうふうに書きたいのだったら、もっと枚数を増やして小説をお書きなさい」
随筆春秋の代表理事である池田さんは、3か月に1度、三軒茶屋の佐藤邸を訪れては、自らのエッセイをお見せして、こんな厳しい指導を受けてきたと聞きます。僕はその池田さんから、口が酸っぱくなるほど、そのへんのことを伝授されています。
さて、僕の祈りですが、実は見事に叶ってきたといえます。北大を卒業し幹部候補生として企業に就職しましたが、結果的に、左遷に次ぐ左遷となりました。42歳で会社を辞する時は実質、現場のブルーカラーでした。お陰で、鼠径ヘルニアと腰痛を背負い込みました。給料も手取りベースで年間500万円には遠く及ばず、金融市場を真剣に勉強せざるを得ませんでした。
その後は、精神的な破綻とも闘い、15年間を無為にしました。神仏は僕に対して親身になって、これでもかと課題を与えてきたのだと信じています。
キリスト教でも、「右の頬を打たれたら左の頬を出せ」「重たい荷物と軽い荷物、どちらを持つかと問われたら迷わず重い方を持て」という教えがあります。
僕は酒が好きでしたから、こんな話を巷のミーハーのおネエちゃんにすると、間違いなく「バッカじゃね!」と笑われたものでした。
これからは、作家見習いとして、これまでに経験したこれらの事を言語化していくのが仕事です。机上で勉強したものと違い、現実に経験した事は、言語化すると莫大な情報量になると僕は思っています。
それをエッセイでいくのか、小説を始めるのか、今は分かりませんが、何かの形で紡いでいくのが、僕の本当の仕事です。
—
文とCG:小倉 一純
宗教妄想)
統合失調症であったといわれるゴッホなどは、作品も売れず、評価もないのに、自分の母親に、「僕は今、描かなくてはならないんだよ」と語っています。『銀河鉄道の夜』の宮沢賢治も、後世に残すべく作品を書いては、大きなボストンバックの中に、原稿をしまい込んでいました。彼らは自分の仕事を天命であると考えていました。下手をすれば宗教妄想ととられかねません。そういえば、かつての角川書店社長・角川春樹も、自分は須佐之男命(スサノウノミコト)の生まれ変わりであると公言していました。僕の場合は現実に宗教と関わりを持ち、自分なりの経験を積んでいます。例えば、以下作品にそのことを具体的に綴っています。
◆「僕の恩師」
⇒ https://www.bungaku-sekai.com/my-teacher/
◆「社員研修」
⇒ https://www.bungaku-sekai.com/kensyu/
◆「日本の行く末を思う、VerUP不能・昭和のオジサン」
⇒ https://www.bungaku-sekai.com/a-showa-era-man-unable-to-update/
宗教本来の目的)
このオッサン、宗教本来のテーマを履き違えとるんちゃうか? とお思いの方もいるに違いありません。その通りです。そもそも、宗教的人格とは、我欲を離れ利他の心を持つということですよね。宗教専従者に「他人様のことをいつも考えていますか?」と問われるのが一番辛かった。末期ガンの患者さんだけを病院に見舞ったりしたこともあった。山奥の全寮制の人間塾で問題のある子の面倒をみたこともあった。どれもこれも真似事に過ぎなかった。人を想うのは難しい。中学生の頃から作家に憧れていた。人間の業をテーマに小説でも書ければ素晴らしい。その場合、宗教心は却って邪魔になると思う。もっとも僧侶で作家という場合もあるが。
遡って、大学時代は座禅をやりました。道場に通って、導師様と禅問答をするわけです。第1問目は、「父母未生以前の己とは何ぞや」。これは禅宗の公案として有名ですね。すべてを取っ払ってもなお残る自分とはどういうものなのですか? という意味です。導師様から合格点をもらえると次の公案へ移ります。そんなのアンチョコでも見て予習すればいいじゃないか、と思われるかもしれませんが、そんなインチキが通じる世界ではありません。宗教における修行を文学にした作品があるといいますが、そういう作品は本質的に書くことはできません。「だって読んだことあるもん」とよくいわれますが、それはそれらしいことが描いてあるだけだと僕は思います。