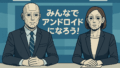Rewrite:ワンイッシュー化された世界とメディア・インターフェイスの構造
—構造の批判が空転する時代—
現代社会の言論空間についてあるジャーナリストの言葉をもとに自分の視点でリライト※してみました。
最近では、ジャーナリズムの言葉がとても難しくなっていて、まるで学生時代に不可をとったドイツ語のように感じられることがあります。情報技術が進むにつれて、言葉が機械や制度に寄り添うようになり、逆に人間の感覚から遠ざかっているようにも思えます。
とくに「インターフェース」という言葉が一般化してから、その傾向が強まったのではないでしょうか。家電のCMなどで聞くようになったのは90年代初頭からで、1995年のインターネット元年以降は、IT用語が日常会話に次々と浸透していきました。
以下の文章ではそうした社会的変化に触れつつ現在の言論空間の構造と問題点について考えてみました。
※ここでいうRewriteとは、リスペクトを含む自学自習の行為です。
***
多くの人にとって、世界は「ワンイッシュー」でしかない。それ以外の問題は視界に入らず、一点集中の意見だけが自我や行動を駆り立てる。
こうした偏在を「嘆かわしい」と思っても、その反論自体がまた別のワンイッシュー化に陥る危うさをはらんでいる。
Facebookでは、旧来のリベラルメディア(新聞・テレビ)やインフルエンサー的ジャーナリズム(疑似マスメディア)が、しばしば「構造的な視点」を示そうとする。しかも、それが一種の「通過義礼的なマナー」と化している。
「構造」とは、週刊誌などでもよく目にする、「権力構造」とか「社会構造」などというときの「構造」と同じ意味である。(つまり、要素と要素がどのように組み合わさってその事象を生み出しているのか、これを構造と呼ぶ)
だが、その語りは実感に根ざすというより、現実から浮いたユートピア的な知のスタイルに映ってしまう。多くの人には「知識の演出」として機能するだけで、心には届かない。
スマホの画面サイズや、X(旧Twitter)の文字制限、切り取られる動画の尺などが、私たちの世界認識を狭くしているといわれる。
しかし実際には、もともと人の認識などそんなに広いものではない。そんな「狭い世界観」にぴったりのユーザー・インターフェイスを私たちは、手に入れただけではないのか。
そうしたインターフェイスは、空間や時間を横断する情報の入口として機能し、発信者や支持者以上に求心力を持つ存在となった。
つまり、入力された情報がネット回線に乗り、独特のアルゴリズムにより、書き手の予想を遥かに超え、勢いよく拡散されていくようになった。
そういう構図は、スマホとTwitterが社会の中心に躍り出た2011年の3.11震災直後から、徐々に形づくられてきた。
以来、メディア・インターフェイス(スマホやSNS)こそが主役であり、言葉や思想の運動はその「設計された窓枠」の中に限られている。
そして、そういうワンイッシュー的な世界では矛盾という概念すら成立しない。前にいったことを簡単に覆しても、「そのときに正しいこと」であればそれでよく、論理的整合性など誰も気にしない。「矛盾している」と知的に指摘したところで通じない。
つまり、1話完結というのが、今時の言論における、定番のスタイルだ。それまでの話とは一切の関係性を持たないのである。
こうしたメディア社会のリアリティを踏まえて、「次にどんな手が打てるのか」を考えることは、とても重要だ。構造の批判が空転する※時代において、届かない言葉の先に何を構築できるか。それが今、問われている。
文とCG:小倉 一純
※構造的に語ることが今時の言論の通過儀礼的なマナーであるのだから、社会を変えるという視点では、それは大した意味を持たないことも多い。従って、その構造的な語りを、さらに批判したところで、それもまた、今時の言論の通過儀礼的なマナーと捉えられてしまう。こういう現象を今時では「吸収されてしまう」と表現する。つまり意味を成さないということである。ではどうすればこんな現状を打破できるのか。構造の外で生の言葉(メタ情報を限りなく背負った)を熱く語り合う場を持つのが一番ではないかと思う。では、それはどこにあるのか? リアルアバターのメタバース空間とかは? 体温や風や匂いはないけど……。キャンプファイアーで殴り合いながら議論して最後に笑って抱き合うとか。