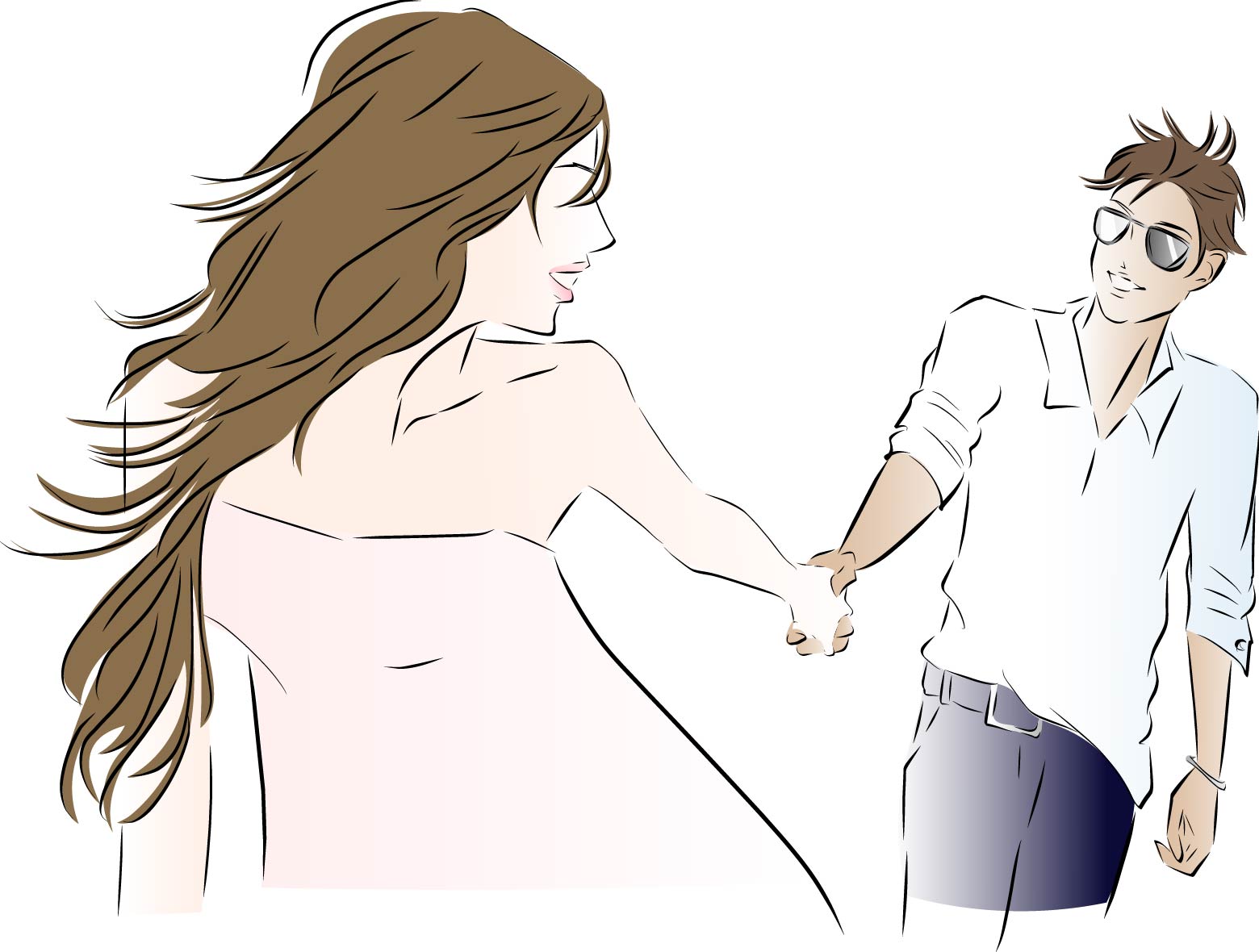【作品紹介】
待ち合わせをした女子がオシャレをしているのを、一体誰のため? と考えるあたり、今思い返しても、僕は人の気持ちの分からない人間なんだな、と思ってしまいます。そんな僕には発達障害があって、五十代になってそのことを専門医から指摘されました。
小倉 一純
【説 明】
—獣医の思い出やウンチク—
作品中の成績がよくなかったから獣医に進んだ、というのは、おかしいではないか、納得できない、といわれることがあるが、これは本当である。我家に高齢の母がいるのだが、そこへ在宅医療の医師が往診してくれている。その先生は、板橋の帝京大学医学部の出身なのだが、僕にこんなことをいった。
「こっちなんか受験時代、帝京を目指してどれだけ苦労したと思ってるんだ! 獣医に入って半年で辞めたなんて聞くと、ふざけるなと思っちゃうよ」
冗談半分にこんなことをいわれた。
「はあ、もうしわけございません」
こう思うしかなかった。
他にもある人生の師から、
「親に安くない学費を出させておいて、あんたは親不孝者だな」
と直言されたこともあった。そういわれると返す言葉がなかった。
獣医学科は、僕が一浪で入学した時に初めて六年制が開始となった。それまでは四年制だった。ちなみに、一九八四年が六年制獣医学部の第一期卒業生を輩出した年度となる。
医学部でも当時の新設校のことはよく分からないが、国公立や著名な私立医科大学、医学部は、その頃の獣医学部よりはるかに難しかったはずである。僕が進学したのは、日本大学農獣医学部獣医学科というところであった。
私立では現在、日本獣医生命科学大学(旧・日本獣医畜産大学|東京都武蔵野市)、日本大学生物資源科学部獣医学科(旧・日本大学農獣医学部獣医学科|神奈川県藤沢市)、麻布大学獣医学部獣医学科(旧・麻布獣医大学|神奈川県相模原市)、北里大学獣医学部獣医学科(青森県十和田市)、酪農学園大学獣医学群獣医学類(北海道江別市)と元総理で凶弾に倒れた安倍さんが新設した岡山理科大学があったと思う。この中でもかつて最も偏差値が高かったのは、日本獣医畜産大学である。
高校時代、同級生だった、石田曜子先生の母校である。その後、東大院でも研鑽を積んでいる。石田先生は、「石田さんッ」と人から呼ばれても返事しないそうである。意地悪や威張っているのではなく、獣医師となってからもう何十年も「先生」とか「石田先生」と呼ばれてきたので、区役所などで「石田さ~んッ!」と呼ばれても、絶対に自分とは思えないという(笑)。この石田先生の書くSNSは、思った以上に面白い。書き筋はなぜか、直木賞作家・佐藤愛子の書くエッセイと似ている。佐藤愛子先生は、僕が所属する、同人誌 随筆春秋の大師匠である。
国公立では、まず東京大学に獣医がある。東大は内部で成績を加味して進学先が決定されるから、どうしても獣医になりたい若者が東大を受験するのは基本的にはNGだと思う。となると、国公立獣医の一番手は北海道大学ということになる。北大では僕の頃から獣医学部の偏差値は同大の歯学部を上回っていた。次が、東京農工大学の獣医だろう。僕は国公立ではこの農工大を受験した。勉強が足らずあっさり不合格となった。
(東京大学農学部獣医学専修)>北海道大学獣医学部>東京農工大学農学部共同獣医学科
国公立で獣医のある大学は、鹿児島大学、宮崎大学、山口大学、鳥取大学、大阪公立大学、岐阜大学、東京農工大学、東京大学、岩手大学、北海道大学、帯広獣医畜産大学などである。
卒業してからは、医師と獣医師では待遇には雲泥の差がある。医師ひとり千五百万円(年収)というのがあるが、獣医は遠く及ばない。行政にも特別職で獣医師の就職先があるが、一般の大卒とほとんど変わらない給料だ。つまり安い。勤務獣医師で一番の就職先はJRAといわれている。中央競馬会である。実質、農林水産省の外郭団体だ。北海道日高地方の浦河町は、サラブレッド(競馬馬)の飼育で有名である。いくつもの個人牧場のほか、このJRAの大規模牧場がある。獣医師も大勢働いているはずである。
僕の頃はご近所さんに獣医というと「何でそんな……?」という返事が返ってくることもままあった。現在では、動物のお医者さんとして、彼らのQOL(生活の質)の面倒みるのが獣医師である、という見方も定着しているが、当時ではまだまだ、産業動物相手のハードな汚れ仕事という見方の方が大勢を占めていた。でも、これが本来の獣医の姿であったし、今でもとても重要な分野である。
このイメージを一気に変えたのが「花とゆめ」という少女漫画シリーズから出た『動物のお医者さん』というコミック漫画であった。舞台は、北海道大学の獣医である。獣医師を、動物のお医者さん、という目で世間が見るようになったのはこの漫画のヒットからである。
ただ当時でも、例えば米国などでは、医師と獣医師のどちらかが見劣りするということはなかったようである。米国では獣医師の社会的地位は日本より断然高いと聞いていた。獣医師にも専門医制度が確立されており、米国では、この専門医の社会的評価が特に高いらしい。昭和の昔、日本では、犬は庭先で飼われていることが多かった。当時の英語教科書に出てくる「ブラッキー」のように、リビングのソファーで人間と一緒に過ごす犬はまだまだ少数派であった。
ちなみに僕の母校である北大(僕は経済学部経済学科出身)では、札幌の広大なキャンパス内に、医学部、獣医学部、歯学部の三つの医師系がすべて揃っている。詳しくしらべたが、これは世界でも北大だけだ。何のメリットがあるのかと問われると僕にはにわかに答えることはできないが、こんなこともあるのではないか、という部分を書いてみる。
北大には「人獣共通感染症リサーチセンター」(旧名称)というのがあるが、ここはウイルス感染症の専門研究機関で、厳重なつくりになっている。獣医学部が音頭をとっていて、ここで、獣医学部、医学部、薬学部、農学部、水産学部と民間製薬会社などがコラボして新薬の開発などを行なっているのだ。コロナ新薬もここで塩野義製薬と一緒になって開発し販売に漕ぎつけた。
これらの学部に通底しているのは、「薬理学」であろうか。日本では馴染の薄い分野だ。「薬理学士」とか、「薬理学博士」など、米国ほか海外にはあるが日本にはない。「薬学」の中でも特化した分野である。例えば、野生動物への環境ホルモンの影響を調べる学問は「毒性学」というが、これなども「薬理学」の一である。北大では学内で学部間の人事交流も行われている。どの程度流動的なのか僕は現実を知らないが、これは、大規模総合大学のメリットのひとつではあると思っている。
本題からはずれるが、要するに、獣医学部だから獣医師になるとか、水産学部だから水産会社に勤務するとか、そういうことではまったくないわけである。例えば、農学部や水産学部でも、海洋生物や農産物に環境ホルモンがどう影響するかを勉強する毒性学の講座などがある。これは、「薬理学」(特定の物質が生体にどう影響するのかその「作用機序」を研究する)の一だから、農学部や水産学部から製薬会社に入社して、癌の新薬を開発するということもあるわけである。
さらに、水産学部などから、出版業界に就職する人もいる。例えば、僕が個人的に面白いと思うのは、医学書院である(ここに北大水産出身者が勤務しているという意味ではない)。とてもユニークな会社だ。医療関係のかなり突っ込んだ書籍を発行している。専門書である。だがそれだけではない。看護と介護を合わせた『ケアをひらく』シリーズなどの出版でも有名だ。このシリーズ45冊(2024年6月時点)は、医療に端を発し文学のレベルにまで達している。「編集者」という仕事が出版には必ずあるが、知的好奇心の旺盛な人には向いた仕事だと思う。そもそも医療関係と文学とはリンクしている。2024年3月に定年を迎えたが、白石正明さんという名編集者が在籍していた。
大切なことを書き忘れていた。野生動物を保護したり、その野生動物がもたらすウイルス感染症から人間を守ったり(防疫)や、その場合の人用の治療薬の開発などは、本来的に獣医師の仕事である。現に、北大の「人獣共通感染症リサーチセンター」(旧名称)の音頭をとっているのも、医学部や薬学部ではなく、獣医学部である。感染症の新薬の開発なども、民間製薬会社とコラボして行っている。その現実は既に書いた通りである。また、牛馬その他の産業動物(家畜)を定期的に診察して、早期に異変を発見し、集団内で感染症が蔓延しない内に、殺処分するなど手を打つのも獣医師の獣医師たる仕事である。つまり、獣医師というのは、人間の幸福を守るため、野生動物や産業動物を適切にコントロールするというのが、その本来の使命だったのである。現在でもそれは変わらないはずである。残念ながら、現在の街の獣医さんでは野生動物を扱える先生はごく少数であるそうだ。たまにTVなどでそういう野生動物の専門家である獣医師が取材されているのを観ることがある。僕らの時代は獣医師といえば産業動物・野生動物の分野での仕事が主流と目されていた。現在では、いろいろな大学の獣医HPを閲覧すると、ペットとしての犬や猫の幸福=QOL(生活の質)を保つための「動物のお医者さん」を育てることも主流になりつつあるようだ。時代も変わったものだと思う。
獣医学部で勉強する内容は、医学部とほとんど変わらない。では何が違うのか。一言でいって「緊張感」だそうである。 でも、重いカリキュラムをすべてこなし、国家試験も突破して獣医師になるのはなかなか大変ではないかと思う。僕には実体験がないので分からない。しかし、その割には報酬も安く、打算的ないい方をすれば、ペイしない。そこが医学部と決定的に違うところである。情熱を持った人が取り組む仕事なのだと思う。
緊張感の件は、高校の同級生で同じ日大の獣医学科で一年先輩だった、渡辺ユキさんから聞いた話である。彼女は卒業後、アホウドリの天然繁殖に人生を捧げた。惜しくも五十代で急逝してしまった。彼女は、同じ同級生の岩田君(当時、日産自動車勤務)と手紙のやり取りをしていたらしい。二人にもそれぞれにパートナーがいた。もちろん、週刊誌が喜ぶような関係ではなかった。その岩田君が段取りをして40歳を迎える前に皆で会って話したことがある。
ちなみに、日本大学の獣医では二年次だったか、夏休みになると、北海道の牧場で泊まり込みで働くという実習があった。提携先の協力・酪農家で実施される大学の正式な授業である。単位が取得できるし、アルバイト料もいただける。二日目の朝などは初日の疲れで食事が喉を通らないという体験談を聞いた。それだけ重労働であるということだ。「直腸検査」といって、利き腕にロングのビニール手袋をして牛の肛門に手を入れ肩まで差し込むという実習もある。格闘技で鍛え腕の太過ぎる人は無理の場合もあるというが、話が少々盛り過ぎの感も否めない。とはいうものの、本当にそういう場合があるという事実を僕は読んだことがある。そんな牧場実習を終えると、北海道一周の一人旅をして戻ることも定番のひとつになっていた。実習を終えてさらに一人前の人間に成長して新学期を迎えることになるのだろう。
近年の北海道の酪農も農業も、機械化と大規模化が目覚ましく進んでいる。一見、よろこばしいことのようにも思えるがその実そうではない。北海道では、かつて経営環境の厳しさから離農が相次ぎ、隣地や近隣の農家や酪農家が、それを買い取り、その後少々無理してでも借金をして大掛かりな機械を導入した。その繰り返しで、現在のように大規模な農場や牧場になっていった、という経緯がある。
これこそ余談だが、母校北大の同級生で北海道で農協の親玉のような金融機関に就職した武田忠義君の話である。彼の実家は、帯広もそう遠くない足寄(あしょろ)というところである。あのフォークシンガー・松山千春の実家もある場所だ。そこで武田君の父親は酪農を営んでいた。個人経営の小さな牧場である。武田君は地元の中学校へ通うのに、自家用車を使っていた。熊が出るので危険だから、「オイ、息子よ、これを使え!」といって彼の父親が中古車を下げ渡してくれたという。もちろん無免許である。武田君曰く、「地元には信号機なんて一箇所もないべやぁ。足寄には法律なんかねぇッ!」。彼は法学部の卒業である。金融機関に就職し帯広で勤務していた彼は、職場で少し年上の女性に見込まれ、所帯を持つことになった。僕もほかの同級生と一緒に帯広に呼ばれて結婚式に参列した。ちなみに北海道の結婚式は漏れなく会費制(当時一人一万円)で、偉い人の冒頭あいさつはなくいきなりカラオケで始まる立食形式である。そのせいか、何度も結婚できるとあって、離婚率が高い。もっともこれは北海道の都市伝説である。
思い出したので書いておく。日本大学農獣医学部獣医学科というのは神奈川県の藤沢市といえば聞こえがいいが、実のところ小田急線の駅で「六会」(むつあい)というところにあり、僕の頃は、駅前のたった一軒のパチンコ屋もつぶれているほど鄙びた場所だった。駅を降りるとすぐに、風向きによっては畜舎の匂いが漂っていた。いわゆる田舎の香水である。入学した初っ端のホームルームでクラス担任がいった。獣医学部の教授のひとりがこのクラス担任を務めていた。長尾先生といっただろうか。これから獣医師の実態を話すから、それを聞いてがっかりしてしまった人はすぐに獣医学科を辞めるようにとの先輩としてのアドバイスだった。
その一は、医学部では若い内に医学博士の称号がもらえるが、獣医学部と文学部だけは五十歳を過ぎても、もらえない人がいる。その二は、獣医師は人間の医師と違って収入が低い。現にその教授は五十歳間近だがその当時、家族で公団住宅(つまりアパート)暮らしであった。その三は、獣医師の仕事は危険のともなうことも多いというものである。
その三だが、例えば、公務員として「防疫」という仕事があるのだが、これを「防疫官」という。「植物防疫官」ともなると港に停泊中の貨物船の船倉にうず高く積み込まれた小麦などを調べるわけだ。その際、下手な外国船であったりすると、本来、船底まで伸びているはずの梯子(階段)が船倉の途中までしか設置されておらず、内部は真っ暗だから、そこから船倉に落下して亡くなるという事故もあったそうなのである。落下による衝撃で、というよりも、小麦の山の中に埋まって窒息するとか、そういう死因も考えられるわけである。
まとめると、獣医師の場合、一. 栄誉と縁が薄い。二. 給料が安い。三. 危険な仕事も多く命を落とすことも。
これを担任である長尾教授が力説していた。つまり、動物が好きで情熱のある人だけ残ってください、というメッセージだった。偉そうなところがなくとてもいい先生だった。この先生だったらずっとこのまま獣医にいたいなとも思った。
獣医師の就職先は意外だが、公務員が多い。日大は私立大学だが、獣医学部の場合、多くの人が獣医師として、公務員の道に進んでいる。卒業生の二、三割とかそんなレベルではなかった思う(興味ある人は自分で調べて欲しい)。先ほども書いたが、地方行政の獣医師枠の特別行政職などもその一である。この仕事も、これまた先ほど書いたが、野生動物がもたらす感染症から人間を守るのが主たる業務である。現在、この分野は人出不足であると聞いている。
僕は、作品にもあるように、一年生の夏で、この日本大学の獣医を辞めてしまった。経緯は作品にも書いた通りである。翌年、北海道大学の文系に進学をした。
獣医について思い出せる限りを書こうと思い筆を執ったが、まだまだありそうなので、思い出す度に加筆していこうと思う。
【追記一】思い出したので追記する。特別行政枠で獣医師が人手不足であるとこの中で書いた。そんな状況であるにも関わらず、獣医師の資格を持った女性が結婚し、そのままその資格がお蔵入りというケースもままあるようだ。医師の場合であれば、そんなことは起こらない。というのも医師の場合、子育てで休業していた主婦が元の医師に戻る場合、さまざまなバックアップサポートがあるそうである。獣医師の場合にはこれがない。
【追記二】獣医師の免許を取るのは、医師免許を取るのに匹敵するほど大変である。にも拘わらず、獣医師の所得は医師に比べて低い。その理由のひとつは、人間の場合、日本では国民皆保険であるが、動物にはそれがない。もし今後、動物が人間の家族として国家にも認知され、日本国動物皆保険となれば、獣医師の収入もグンとアップするはずである。もっともそうはならないであろう。
【追記三】高校の同級生で日大獣医で1年先輩となった、渡辺ユキさんについて書いておこうと思う。以降は下記URL参照のこと。https://www.bungaku-sekai.com/memory-of-yuki-watanabe/
※以上は私、小倉の色眼鏡でみた内容である。最新情報ばかりでもない。関心のある人は自分で取材してみて欲しい。
小倉 一純
【後 記】
僕がこの仕事に未練があるのかといえば、確かに未練はある。ただ、獣医にだけなりたかったわけではなく、もちろんできれば医者にもなりたかったし、大企業のサラリーマン、例えば、海外勤務や海外出張をバリバリこなす、二十四時間働ける男にもなりたかった。僕の場合は、四十二歳まで健常者として会社員人生を送っていたが、三十歳の頃、一度、メンタル面で大きく破綻したことがある。後年五十歳を越えてからは、専門医に障害を指摘されている。ASDとADHDの併発である。僕自身が社会人年齢であった頃は、自分を鳥観図のように俯瞰することができないから、「俺はどうしてダメなんだ」とむきになり、石に齧りついてでも仕事をしてやろうという過熱した気持ちがあった。六十五歳を回った現在、自分の過去を振り返ると、僕自身、端から無理なことに挑戦していたのがよく理解できるようになった。では、といって、若い内から、つまり大学を出た時点で、なんらかの生業を持つ社会人として世の中に立つことを諦めていたら、今の僕さえなかったのではないだろうか。
そんな僕は、こうすれば成功するということを後輩に指南することはできない。僕自身、成功者になったことがないからだ。だが、こうすれば失敗する、という情報は持っている。おそらくどんな人よりもそういうデータベースを僕は持っているのではないだろうか。ただそれを健常者にも理解できる形で列挙するのは、今のところ難しい。言語下の情報が圧倒的に多いからである。僕の拙い作品をその一助としていただければありがたいと思う。
小倉 一純
ここからは小説である。その一部を掲載した。一冊の本にするつもりだ。――僕が獣医に進んだのは、高校時代にできた彼女が、開業歯科医の娘で、しかも、しばしばこんなことをのたまわったからである。「わたしいっ、サラリーマンの奥さんには絶対なれないと思うのッ」一度や二度ではない。何度も同じフレーズを聞かされた。僕は純文学に興味を持ち、そのせいもあって、ほとんど勉強していなかった。それでも彼女の希望を叶えるために、獣医ならなんとかなるかもしれないと思った。僕らが通っていたのは都立でも、当時は進学校の部類に入る高校だった。その頃の僕の気持ちでは、彼女との結婚は、すでに織り込み済みであった。いざ、その受験が近くなると、彼女から、僕の浮気を指摘され、その後別れをいい渡された。あれが浮気なのか? と思い当たることはあったが、彼女のいい分はいいがかりに近いものであった。年を越せばもうすぐそこが獣医学部の受験だというのに、一体僕はどうすればいいのか。三行半(みくだりはん)を突きつけられた彼女からの電話の翌朝、母が出してくれた朝食の玉子焼きからもうもうと湯気が上がるのを見て僕は猛烈に腹が立った。八つ当たりの心境である。女なんてまったく勝手なものだと思った。だから女はだめなのだ。女は感性だというが、要するに、時々で、自分に都合のいい事をいうだけの下等な生物であるに違いない。例えば、そんな女が政府の要職などに就くべきではない。できれば、この気持ちを、蓮舫と辻本さんと土井たか子の前でぶちまけてやりたい。
小倉 一純